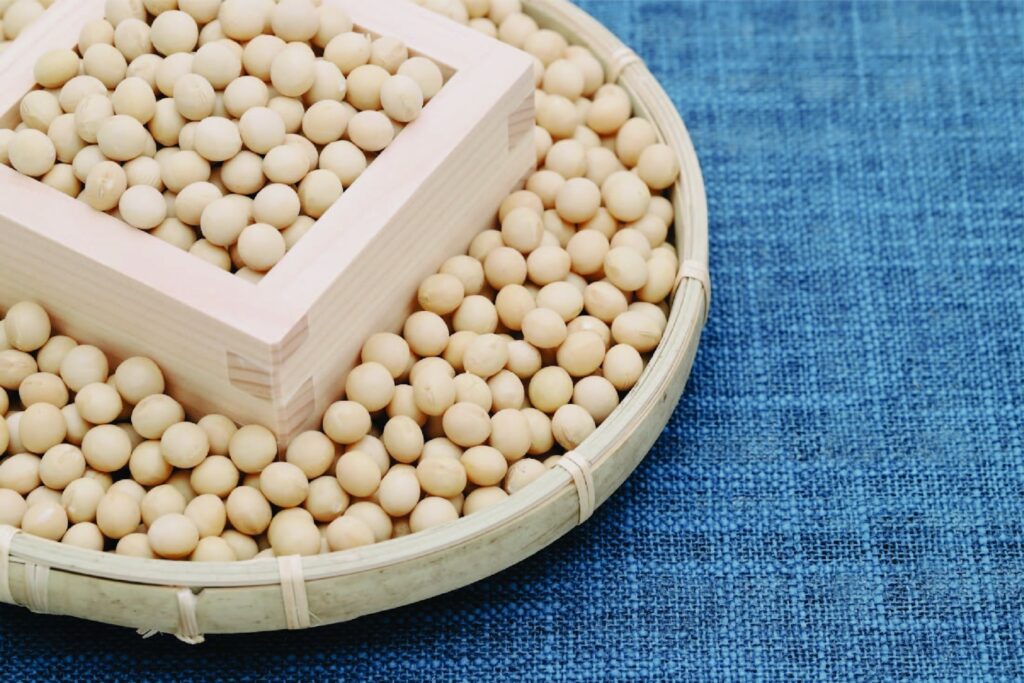BLOG -SDGs and Sustainability
SDGsに通ずるユニバーサルデザインとは?原則や実例を解説
Wednesday, 17 May 2023

今回はユニバーサルデザインの原則や実例、バリアフリーとの違いなどを解説します。
ユニバーサルデザインとは?
まずは、ユニバーサルデザインの定義や混同されがちな「バリアフリー」との違いを確認していきましょう。
すべての人が使いやすいよう配慮されたデザイン
ユニバーサルデザインは「普遍的なデザイン」という意味を持ち、年齢や性別、国籍、障害の有無に関わらず、すべての人が使いやすいよう配慮されたデザインのことです。製品に限らず、建物や施設、環境に加え、構造やシステムなども含まれます。
例えば、ベビーカーや車いすを利用している人でも無理なく使える自動ドアなどは、ユニバーサルデザインのひとつです。
バリアフリーとの違い
ユニバーサルデザインとバリアフリーは混同されがちですが、これらは異なるものです。バリアフリーは、障害があることを前提として障壁(バリア)を取り除くといった考え方を指します。
また、高齢者や障害者などが日常生活の中で感じる心理的な障壁をなくす意味でも使われる言葉です。
一方、ユニバーサルデザインは障害の有無に関わらず、初めから誰もが使いやすいようにデザインする点がバリアフリーとの違いです。
(参照:ユニバーサルデザインを知る)

ユニバーサルデザインの7つの原則
ユニバーサルデザインの方向性を明確にするために定められた7つの原則があります。ユニバーサルデザインの提唱者であるノースカロライナ州立大学のロナルド・メイス教授をはじめ、建築家やデザイナーなどが話し合い、まとめたものです。
1.誰でも公平に利用できること
人によって状況が違っても、誰もが公平で同じように使えること。かつ容易に利用できることが求められています。
2.使う上で自由度が高いこと
使う人の能力やさまざまな好みなど多様性に対応できるよう、自由度が高く作られていること。差別なく誰でも使えることが条件になっています。例えば、右利き左利き両者とも使えるハサミなどがあります。
3.使い方が簡単でわかりやすいこと
使う人の言語能力や知識、経験などに関わらず、誰にとっても使い方が簡単でわかりやすいこと。例えば色分けなどの工夫によって直感的に使えることなどが挙げられます。
4.必要な情報がすぐ理解できること
使う人の聴覚や視覚の能力、使用状況に関わらず必要な情報が伝わり、理解しやすく作られていること。例えば歩行者用の信号は、渡れる合図として青く光り、音が鳴る信号は視覚に障害がある人にも伝わります。
5.うっかりミスや危険につながりにくいデザインであること
うっかり間違った行動をとってしまっても、危険につながりにくく作られていること。例えば自動消火機能付きのガスコンロは、火の消し忘れによるガス漏れ事故を防ぐよう工夫されています。
6.体への負担が少なく無理せずに使えること
無理のない姿勢や少ない力で使えるデザインであること。例えば、蛇口をひねるタイプの水道はある程度力が必要ですが、レバーを下げるタイプの水道は体への負担がかかりません。
7.利用しやすい十分なスペースが確保されていること
どんな体格や姿勢、移動手段でも利用しやすい十分なスペースが確保されていること。多機能トイレや駐車スペースなども、誰でもアクセスしやすく利用しやすいことが求められています。
(参照:ユニバーサルデザイン7つの原則)

SDGsとユニバーサルデザインの共通点
SDGsでは誰一人取り残さない社会を作ることを掲げており、ユニバーサルデザインは、誰もが使いやすいデザインを目的としています。
製品だけでなく、施設や環境、システムにおいても、誰もが利用しやすく、安心して暮らせる社会を目指している点が、SDGsと共通した考え方といえるでしょう。
特にSDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」のターゲットには、すべての人が安全かつ安価で利用できるシステムや公共スペースの提供が求められており、目標達成にはユニバーサルデザインの推進が必要不可欠であることがわかります。
(参照:11.住み続けられるまちづくりを)
(参照:ユニバーサルデザインについて)

私たちの暮らしの中にあるユニバーサルデザインの実例
私たちが普段過ごしている街や家の中にも、実はユニバーサルデザインが数多く存在しています。ここではその一例をご紹介します。
街の中にあるユニバーサルデザイン
・点字ブロック
・自動ドア
・段差のない歩道
・センサー式蛇口
・自動販売機
・ピクトグラム
公共のトイレの手洗い場では、手をかざすだけで水が出るセンサー式蛇口が普及しています。また、最近の自動販売機は誰もが利用しやすいよう、商品のボタンが低めに設置されているなどの工夫がされています。
加えてピクトグラムは情報や注意を示す絵文字のことで、日本語がわからない外国人や視力が低下している高齢者にもわかりやすいデザインが特徴です。
家の中にあるユニバーサルデザイン
・利き手の区別なく使える文房具
・シャンプーやリンスのボトル
・テレビの字幕放送
・紙幣
シャンプーボトルの側面にはギザギザの刻みが施されており、触っただけでリンスとの区別がつくよう工夫されています。
また、紙幣には手触りでお札の種類がわかる識別マークがついており、ユニバーサルデザインが取り入れられています。
(参照:こおりやまユニバーサルデザイン)

SDGs「誰一人取り残さない社会」の実現にはユニバーサルデザインが必須
SDGsが掲げる「誰一人取り残さない社会」の実現にはユニバーサルデザインの推進が必要です。国や企業に「こうしたらもっと良くなる」といった声を届けるのも良いでしょう。
そしてお互いの違いを尊重し合い助け合う、心のユニバーサルデザインも大切にしていきましょう。
あわせて読みたい: SDGsに貢献!ヘアドネーションで頭髪を失った子どもたちの未来を守ろう