BLOG -Circular Economy and Environment
脱炭素化に向けて電動バイクの開発が加速!日本の現状と将来の展望
Thursday, 20 February 2025

今回は「乗り物の脱炭素への取り組み」をテーマに、電動バイクの開発が進む背景や、電動バイクで改善できる環境問題、電動バイクの現状や将来の展望を解説します。
日本で電動バイクの開発が進む背景
日本のバイクメーカーが電動バイクの開発を進める背景にあるのが、「バイクの2035年問題」です。これは東京都の脱炭素社会を目指す取り組み「ゼロエミッション東京」の中で掲げた「2035年以降、新車の二輪車すべてを非ガソリン化する」という宣言を指します。
つまり、2035年以降はガソリンを燃料としたエンジンバイクを販売しないということです。この発表を受け、各バイクメーカーは電動バイクの開発に力を入れ始めました。
複数のメーカーが「2035年までに主要機種の新車を電動化する」と発表しており、電動バイクの生産は急速に進んでいます。
(参考:https://www.kankyo1.metro.tokyo.lg.jp/archive/vehicle/sgw/promotion/evbike_batteryshare.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB084YC0Y0A201C2000000/)
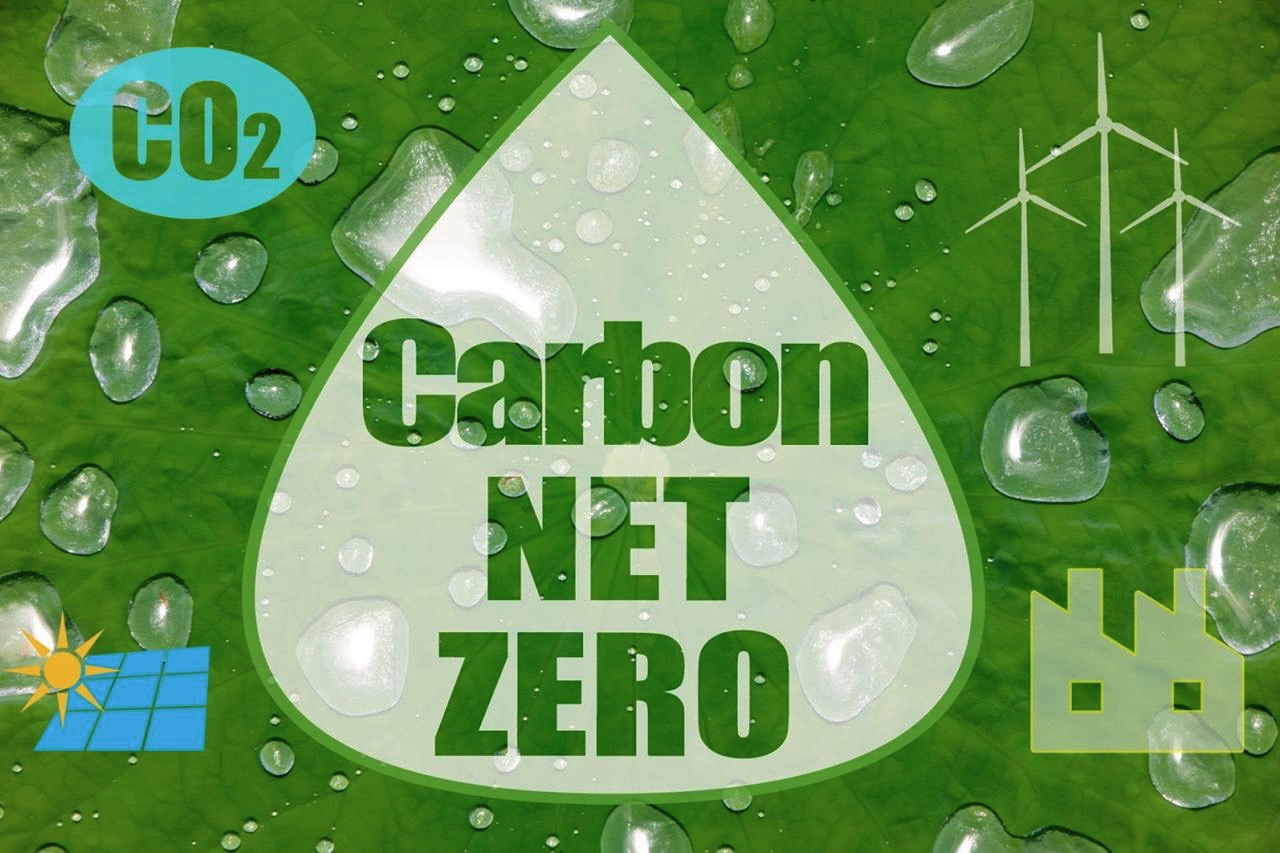
電動バイクへの移行で改善できる問題
電動バイクへの切り替えによって、環境問題の改善につながるといわれています。具体的にどのような問題を解決できるのか見ていきましょう。
<走行中のCO2排出量を削減できる>
電動バイクは走行中に二酸化炭素(CO2)を排出しないため、エンジンバイクに比べて大気中のCO2排出量を削減できます。
また、電動バイクへの電力補給を再生可能エネルギーにすることで、全体的なCO2排出量も削減でき、温暖化の抑制に貢献します。
あわせて読みたい: 気候変動対策!エコドライブのメリットやポイントを解説
<排気ガスを出さないため大気汚染改善に貢献>
電動バイクは排気ガスを出さない点も特徴のひとつです。ガソリンを燃料とするエンジンバイクは、窒素酸化物(NOx)を多く排出し、乗用車の約2倍、大気を汚染するといわれています。
大気汚染は自然環境や人体への被害など多くの影響を及ぼすため、改善すべき課題です。電動バイクへ切り替えることで、これらの被害を軽減できます。
(参考:「二輪車はSUVなどの10倍、大気を汚染」LAタイムスが指摘)
<騒音を低減できる>
電動バイクは車体に積んだバッテリーから電力を流し、モーターを回転させて動くため静かに走行できます。多少のモーター音のみで、エンジン音やマフラー音が鳴らないため、騒音問題が改善できるのもメリットです。
<エネルギー資源の消費量を削減できる>
電動バイクはエネルギー資源の消費量削減にも貢献します。電動バイクに欠かせないバッテリーの技術は年々進化しており、今後再利用できるバッテリーも登場すると考えられています。資源の循環利用は、脱炭素社会の実現に重要な要素です。
(参考:https://www.life-evmotorcycle.com/basicknowledge/spread.html)

電動バイクの現状
電動バイクは高価な印象があるかもしれませんが、エンジンバイクの車体価格や初期費用とほぼ変わらず、相場は20万円前後です。
また、電動バイクは燃費が良く、ガソリンよりもランニングコストを3分の1ほど安く抑えられます。
しかし各メーカーからさまざまな電動バイクが開発されているものの、日本では電動バイクの普及率が低いのが現状です。

電動バイクの課題
日本で電動バイクが普及しづらい理由は、航続距離の短さや充電インフラの不足などの問題が関係しています。ここでは電動バイクに関する課題を確認していきましょう。
<航続距離が短い>
電動バイクの航続距離は、種類やバッテリー容量によって異なりますが、一回のフル充電で約30〜40kmが多く、エンジンバイクの10分の1程度しか走行できません。
通勤や通学など日常生活における短距離の移動は困らないものの、旅行やツーリングなど長距離の移動には不向きといえます。
航続距離を伸ばすには大容量のバッテリーが必要ですが、車体重量が増えるほど航続距離が短くなる点が難題です。
(参考:https://techtimes.dexerials.jp/electronics/e-bikes-and-surface-mounted-fuses/)
<充電インフラの不足と充電時間の長さ>
電動バイクの充電ステーションが十分に整備されていない地域が多いのも、課題のひとつです。外出先で充電が必要になった場合、周辺に充電設備がなく不便を感じるかもしれません。
また、電動バイクは充電に時間がかかります。急速充電でも40〜60分はかかるでしょう。こうした利便性の低さが、普及が進まない理由になっています。

電動バイクにおける将来の展望
航続距離や充電に関する課題を持つ電動バイクですが、各バイクメーカーや部品サプライヤーは技術開発を続け、新たな取り組みを始めています。
例えば各社のバッテリー規格の共通化や、バッテリー交換ステーションの設置です。共通仕様のバッテリーのシェアリングサービスによって、外出先でも短時間でバッテリーを交換でき、長距離移動も可能になります。
現在は東京都と大阪、埼玉の一部地域に設置されていますが、今後ステーションの設置エリアを拡大していくとしています。
バッテリー循環利用の仕組みを構築することで、電動バイクにおける航続距離と充電問題を解決し、電動バイクの普及を推進していく方針です。
また、東京都では脱炭素化に向けて電動バイクを購入する事業者や個人に対し、経費の一部を助成する制度を実施しています。

政府の支援策や企業の取り組みで電動バイクの普及は広がる可能性大!
走行中にCO2や窒素化合物を排出しない電動バイクは、温暖化や大気汚染を改善する、環境や人に優しいバイクです。
航続距離が短く、充電に時間がかかるといった課題はありますが、政府の支援策や各メーカーの改善策によって、今後電動バイクの普及は広がっていくことでしょう。
バイクを検討している人は2035年問題も視野に入れ、電動バイクを選んでみてはいかがでしょうか。









