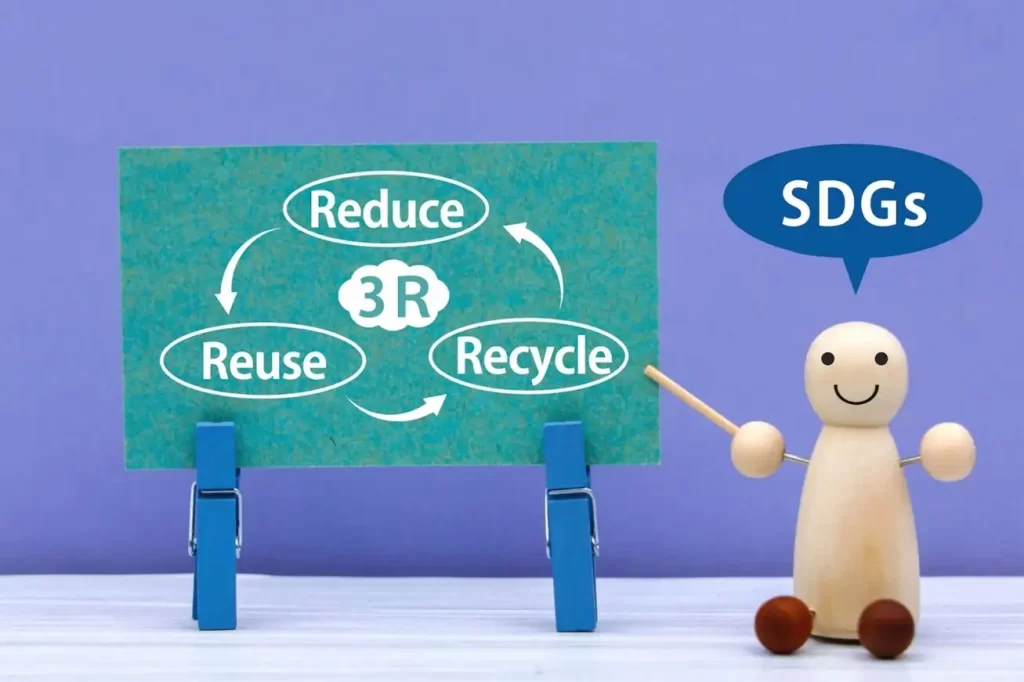BLOG -Plant-Based products
プラントベースフードで広がる食育の可能性|実践方法も解説
Friday, 28 March 2025

今回はプラントベースフードが食育に適している理由や、プラントベースフードを導入した食育の事例、家庭での実践方法を解説します。
プラントベースフードと食育の関係性
食育とは、食べものや食事に関する知識や正しい選択を身につけ、健康的な食習慣を育むための教育を意味します。
栄養バランスのとれた食事を学ぶだけでなく、「何を・どのように・なぜ食べるのか」の理解を深め、食を通じて心身の健康や社会・環境への影響を考える力を養うというのが目的です。
また、近年は食品ロスや持続可能な食材選び、農業や食料生産などのテーマが加わり、サステナビリティの観点からプラントベースフードに関する食育も注目されています。
(参考:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/3.html)

プラントベースフードが食育に適している理由
プラントベースフードが食育に有効と考えられています。ここではプラントベースフードが食育に適している理由を見ていきましょう。
<子どもの味覚形成と栄養バランスが補える>
現代の子どもたちは栄養バランスを崩しやすい環境と考えられています。菓子パンやインスタント食品、ファストフードといった手間なく食べられる加工食品が普及したことで、野菜や穀物などを食べる機会が減っているからです。
また、デジタルに熱中する時間が増えて運動不足になり、食欲がわかないという理由で十分な栄養が摂取できないケースもあります。
プラントベースフードは、このような栄養バランスを崩しやすい現代の子どもたちの健康をサポートする食品として注目されています。
植物性タンパク質やビタミン、食物繊維などを摂取できるプラントベースフードは、大豆や穀物類を使用しているため、味覚形成やあごの発達にも役立ち、子どもの成長促進にも効果的です。
(参考:子供の野菜不足とプラントベースフードが果たせる役割について)
<環境負荷を減らす食事の選択になる>
植物由来のプラントベースフードは、環境負荷を減らす食事の選択肢になることを知り、従来の食生活の背景にはどんな環境問題が潜んでいるのかを学ぶ機会になります。
世界で排出されている温室効果ガスのうち、20%は畜産業によるものといわれています。また、畜産業では飼料となる穀物を生産するための広大な土地や大量の水が必要で、森林伐採や水資源の枯渇が深刻な状況です。
肉や乳製品の消費が地球温暖化や資源の枯渇と関わっていることを知り、地球環境に配慮した消費行動を考えるきっかけになります。
(参考:https://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/chikusan/attach/pdf/index-11.pdf)
<動物福祉・倫理的観点を学ぶ機会になる>
プラントベースフードの食育を通じて、子どもたちが食と動物、環境のつながりを理解し、倫理的な視点を身に着けることができます。
例えば、私たちが普段食べている肉や乳製品、卵はどのように生産されているのかを知ることです。
狭いケージで飼育されたり、ホルモン剤や抗生物質を投与されたりといった工業畜産の実態を学ぶことで、動物の命や福祉について考えるきっかけになります。
動物を犠牲にしないプラントベースフードという食の選択肢を知り、個人の倫理観に基づいた選択ができるようになります。

学校におけるプラントベースフードを導入した食育の事例
日本でもプラントベースフードを取り入れた食育を実施する学校の事例があります。ここでは代表的な事例を2つ見ていきましょう。
<プラントベースフードについて学び、植物由来の弁当づくりも>
東京都足立区内の小学校では、小学校3~6年生とその保護者を対象とするプラントベースフードを取り入れた食育が実施されました。
プラントベースフードを展開する企業と共同で行われたこのプログラムでは、食事の一部をプラントベースフードに置き換えることで、削減できる温室効果ガスの排出量を具体的に示すなどして、新しい食の選択肢の重要性を伝えました。
また、プラントベース食材を使った弁当づくりも実施するなど、植物由来のプラントベースフードのおいしさも体験できる食育プログラムの事例として注目されています。
(参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000075782.html)
<プラントベースフードを食べて学ぶ食育プログラム>
学生の好みに合わせた商品やレシピを提案し、学校給食や調理実習でプラントベースフードを実際に食べて学ぶという、食育プログラムがあります。
学ぶパートでは環境負荷の問題や食料問題、フードロス問題などを学び、私たちの食生活が社会課題問題とつながっていることを深く理解するという内容です。
また、食べるパートでは、プラントベースフードを導入した給食メニューを提供し、新たな食体験を通じて持続可能性やSDGsに対してアクションを起こすきっかけづくりを与えています。

家庭でできる!プラントベースフードの簡単レシピと食材選び
プラントベースフードを取り入れた食育は家庭でも取り組めます。ここでは大豆ミートを使った簡単レシピと食材選びを紹介します。
<大豆ミートのキーマカレー>
ミンチタイプの大豆ミートで作る、プラントベースのキーマカレーです。フライパンを熱してオリーブオイルを入れ、みじん切りにしたにんにく、たまねぎ、椎茸、大豆ミートを入れ炒めます。
カレーパウダーやクミンパウダー、塩を入れてさらに炒め、ホールトマト、ウスターソースで水分が飛ぶまで煮込めば出来上がり。動物性の肉不使用でも食べ応え抜群のキーマカレーが楽しめます。

プラントベースフードを取り入れた食育は倫理的観点が育つ
プラントベースフードの食育を通じて、「食べることは健康・環境・動物・社会にどう影響するのか」を考える習慣が身につきます。これによって子どもたちは、食の選択は自分の価値観を表現することでもあると理解し、倫理的な選択ができるようになるでしょう。
学校や家庭でぜひ、プラントベースフードを通じた食育を実践してみてはいかがでしょうか。