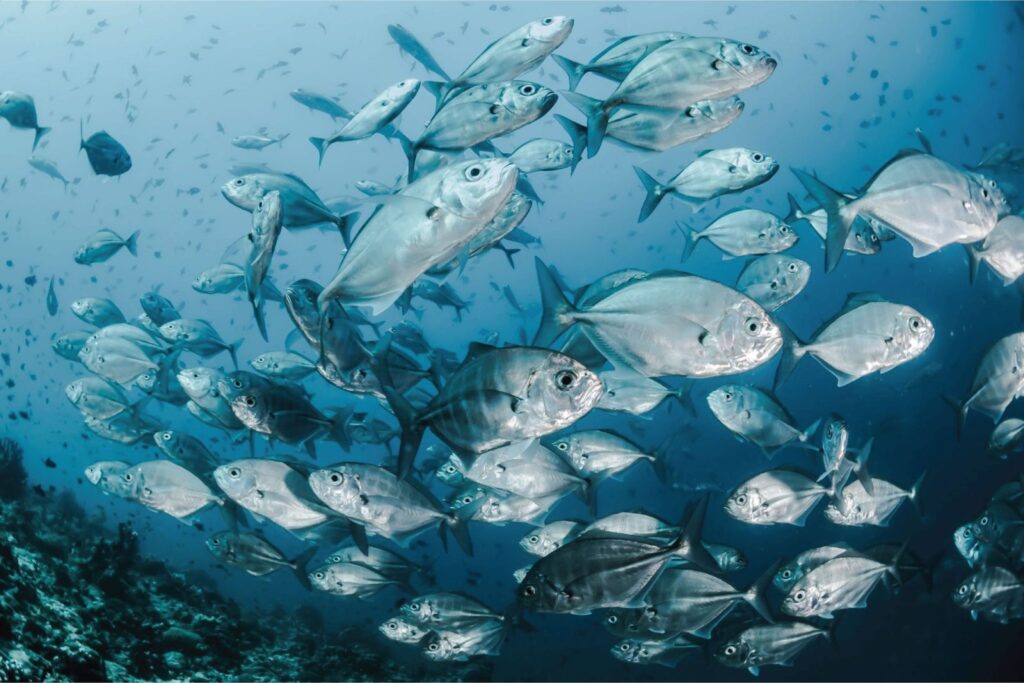BLOG -SDGs and Sustainability
自治体が推進するサステナブル投資|現状と成功事例を解説
Monday, 19 May 2025

自治体がサステナブル投資を取り入れることで、地域の課題解決や経済活性化に寄与することが期待されているのです。
今回は、自治体によるサステナブル投資の成功事例を紹介し、その要因や今後の展望についてわかりやすく解説します。
自治体におけるサステナブル投資の現状
サステナブル投資とは、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)といった要素を考慮し、持続可能な社会の構築を目指す投資手法です。
自治体はサステナブル投資を推進することで、環境問題や社会課題の解決に貢献したり、資金を調達したりできます。
まずは自治体におけるサステナブル投資の現状を見ていきましょう。
<国内機関投資家のサステナブル投資残高の現状>
日本サステナブル投資フォーラムの調査によれば、2023年3月末時点での国内機関投資家によるサステナブル投資残高は約537兆5,908億円に達し、前年から8.9%増加しました。
これは総運用資産残高の約65.3%を占めており、サステナブル投資が国内の投資活動において主要な位置を占めていることを示しています。
この増加の背景には、気候変動や人権問題への関心の高まり、SDGs(持続可能な開発目標)の浸透、そして企業経営や投資行動における持続可能性の重要性の認識が広がったことが挙げられます。
特にESG(環境・社会・ガバナンス)要素を考慮した投資手法が広がりを見せている傾向です。
(参考:https://japansif.com/archives/2830
https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/148.html)
<自治体によるESG債の発行動向>
自治体もサステナブル投資の一環として、ESG債の発行を積極的に行っています。ESG債は、資金使途を環境改善や社会課題の解決に特化した債券で、主に以下の3種類があります。
・グリーンボンド…環境関連事業に資金を充てる債券。
・ソーシャルボンド…社会的課題の解決を目的とした事業に資金を充てる債券。
・サステナビリティーボンド…環境および社会的課題の両方に資金を充てる債券。
例えば2022年には東京都、埼玉県、長野県、福岡市など18の自治体がESG債にあたるSDGs債を発行しています。中でも福岡市は2022年1月に初のグリーンボンドを発行すると、50億円の募集に対して約798億円の応募があり、発行額の約16倍の需要を記録しました。
この資金は省エネルギーに配慮した庁舎整備や地下鉄事業などに充てられています。このように自治体によるESG債の発行が全国に拡大しています。
(参考:https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/434167/011100202/

自治体のサステナブル投資成功事例
自治体のサステナブル投資の成功事例として、ここでは「東京都のグリーンボンド発行」と「長野県のグリーンボンド発行」としての取り組みを見ていきましょう。
<東京都のグリーンボンド発行>
東京都は2017年に日本の自治体として初めてグリーンボンドを発行しました。初回の発行では200億円を調達し、資金は以下のような環境対策事業に充てられました。
・五輪関連施設の環境対策…2020年東京オリンピック・パラリンピックに関連する施設の環境性能向上。
・スマートエネルギー都市づくり…再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の高い都市インフラの整備。
・気候変動への適応策…中小河川の整備など、気候変動による影響を軽減するための施策。
・公園整備による緑化推進…都市部の緑地拡充による環境改善。
その後も東京都は毎年グリーンボンドの発行を継続し、2022年には約400億円を発行しています。さらに2022年10月には自治体として初めて海外市場向けのSDGs債「東京サステナビリティーボンド」を起債し、海外からの資金調達にも成功しました。
(参考:https://business.ntt-east.co.jp/bizdrive/column/post_168.html
https://financial.jiji.com/long_investment/article.html?number=779)
<長野県のグリーンボンド発行>
長野県は2050年に二酸化炭素(CO2)排出量実質ゼロの達成と、気候変動に伴う自然災害の被害軽減を目指し、2020年10月に50億円のグリーンボンドを発行しました。以下は主な資金使途です。
・再生可能エネルギーの推進…県内の河川を利用した「小水力発電所」を新設し、再生可能エネルギーの普及を図っています。
・クリーン輸送の促進…クリーン輸送の促進のひとつに、「しなの鉄道の車両更新支援」があります。地域鉄道であるしなの鉄道の老朽化した車両を新型車両に更新するための補助を行い、公共交通機関の利便性向上と環境負荷の低減を目指しています。
・エネルギー効率の向上…県有施設の設備更新として、空調設備の更新、証明のLED化、高断熱化などを実施し、エネルギー消費の削減を図っています。
・気候変動への適応策…気候変動の適応策として、交通インフラの整備を行います。信号機の電源付化装置の設置や道路防災工事(法面工事など)を行い、交通インフラの耐久性を向上させます。また、水害対策のための河川改修もそのひとつです。河川の拡幅や掘削工事を実施し、水害リスクの低減を図ります。

自治体におけるサステナブル投資の成功要因と課題
自治体におけるサステナブル投資の成功要因として、官民連携による資金調達とプロジェクト推進、明確なビジョンと戦略的な計画率案が挙げられます。
あわせて読みたい: 地域社会におけるサステナビリティとは?企業が取り組む理由と事例
一方、課題としては投資対象の適切な評価と透明性の確保、持続可能な資金調達手段の確立が指摘されています。
今後はサステナブル投資を活用した地方創生の可能性や、政策的支援と規制緩和による投資促進が期待できるでしょう。
地域の活性化や経済成長に寄与する自治体のサステナブル投資に、今後も注目していきましょう。